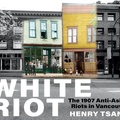僕はまったくの偶然から、ジャズ・ピアニストの赤城恵と知り合いになった。
きっかけは、僕の英語学校にちょっと変り種の新入生が入学したことから始まった。その新入生とは、仙台で活躍するクラシックの作曲家・本間雅夫さんだ。外国人の友人たちと英語で話が出来るようになりたいというのが、彼が英語を勉強する気になった動機だ。他の教師たちは、本間さんは中年にしては覚えが早いと言っていた。そんな訳で、僕も彼と知り合いになりたかったわけだ。
確かに、彼の文法構造を素早く把握できる能力には感心した。ちょうど僕は東北の小旅行から帰ったばかりだったので、その話を彼にした。そうしたら、彼も小説家・太宰治の故郷金木にほど近い青森出身だと言うではないか。
すっかり意気投合して、個人的なことをいろいろ教えてもらった。なんでも彼の奥さんの真理さんは、父親の泰(タイ)さんが大学の博士課程で学びながら、日系人のキリスト教会で牧師をしていた関係で、アメリカのクリーブランドに16年間住んでいたと言う。米国のクリーブランドに日系人のコミュニティーがあったなんて驚きだった。僕と彼の家族が共通点を持っていることを発見して、本間さんに一層親近感を抱いた。
僕たちは、ある授業で音楽について語り合った。話題が最近僕がもっぱら聞いているジャズにいきついた。「僕の義理の弟が、来週コンサートをするんだけど」と本間さんは言う。彼は控え目に、「義理の弟の恵がCDを出しているからコピーしたいか」と言う。僕は嬉しかった。「ミラー・パズル」(音の探求)は最近聞いた沢山のジャズCDの中でもきわだっている。今風の軽快なビーパップが、従来のものと見事に調和しているのである。
コンサートは東北大学の北平キャンパスから遠くないイタリア・レストラン「バリンカ」で開かれた。変った感じの二階建てのビルは、「バンクバーのペンティクトンでデザインされたものだ」とオーナーの小関康さんは教えてくれた。
本間さんは夕食込みのチケットの「7,000円」という値段に恐縮していた。しかし実際のところ、それほど高くないと思う。バリー・ルイスと奥さんのマリコが仲間に加わった。バリーは英語を教え、またフラメンコのギターを弾いたり教えたりもする。僕はバリーに、「恵は今までに聞いたことのあるどのジャズピアニストにもひけをとらない」と請け合っていた。
イギリスのチェルテンハムから来ているバリーは、日本にいて芸術を志す多くの外国人と同じ問題を抱えている。つまり、音楽活動とよい収入になる英語教師の職の狭間で悩んでいるのだ。地方都市の仙台に住むことは、芸術をめでるのに多くの出費をしている。語学教師のアシスタントをやっている知ったかぶりのガイジン芸術家もどき以外には、さして見るべきものもない。僕達のほとんどが趣味にとどまり、四六時中「それ」に時間を費やせるプロたちに、ちょっとした嫉妬の念を抱くのである。
* * *
6時半に開場となった。僕達は早く着いた。部屋の前には黒いヤマハのピアノがあった。1階には約30席、そしてロフト・エリアには本間さんと奥さんの真理、クラシックのピアニスト、家族と友人の方々がすでにおられた。
恵が入って来た時、見つけるのは簡単だった。彼はモス・グリーンのTシャツにジーンズ、ランニングシューズという出で立ちだった。長いポニーテールが肩にかかり、そして長いショールダーバッグを持って来ていた。彼は気軽に客席の方に微笑みかけ、兄弟や友人に会うために階段を駆け上がって行った。その後、本間さんは恵と一緒に下の階に降りてきて、私達に紹介してくれた。恵は完璧にカリフォルニアの気のいいヤツという感じで、ジャズミュージシャン特有のしゃべり方をする。
食事はすごく美味しかった。見渡して分かったのだが、僕達のテーブルが唯一ワインを飲んでいた。特別サービスの一杯を早々に飲み終え、バリーがチリ産のものとなにがしかフランス産のワインを頼んだ。観客は礼儀正しくておとなしく、クラシックの観客のような装いだった。彼らは故郷を錦で飾ったこの道楽息子の帰還に、絶大なる賞賛を送っていた。
「あいつは日本人じゃないよ。君とよく似ている。」
突然バリーの口から言葉がもれた。振り返って僕の方に向けられた顔は赤く上気していた。
僕は奇妙な言葉に不意をつかれた。その後その言葉について考え、そして不思議に思ったのは、恵や僕が聴きながら育った音楽が、日本の聴衆にどうしてこんなによく理解されるのだろうということだ。更に、イギリスのチェルテンハム出身のパリーが、僕の音楽の触手をくすぐるゴスペル、モータウン、ブルース、ファンキー、R&Bをどうしてこんなに満遍なく共有できるかという不思議さだ。おそらくこの辺に、バリーをしてこのこの奇妙な感想を吐かせた理由があるのだろう。
ところで一体「日本人」とは何なのかと、僕はまたしても考え込んでしまった。バリーの奥さんは中国系日本人で、彼女の家族は日本への同化を全うすべく、姓を「林(ハヤシ)」に変えようとしている。僕は日系人だが、恵という「日本人」は、この二つの文化にすっぽっりうまくおさまり居心地よさそうに見える。
舞台の合間に恵が話をしにテーブルのところに来た。彼はクラブの近くで育った、と言う。覚えているのは通りがまだ舗装されておらず、米兵が施しものをくれるヒーローを演じキャンディーを子供たちに投げ与えていた事や、初めて見た地元のレストランのテレビの事さえ覚えていた。彼はその頃の事を淡々と話す。
恵の音楽経暦はちょっとすごい。マイルス・デイビスとの共演に加え、12年以上にわたりスタンレー・チュレンタイン、アート・ペッパー、ジョー・ファレル、渡辺貞夫、エアート・モレイラ、アル・ディメオラ、アラン・ホールドワースら、その他ジャズ界の大物と共演してきた。
恵の姉は言う。子供の頃、彼らは勉強の事では無理強いされたことはなかったが、恵は絶対に勉強はしたがらなかった。「彼は反抗的だったわ。クラシックの代わりにジャズを選んだの。」
恵は仙台に生まれた。4歳の時、恵の家族はクリーブランドのヒュー地区に引っ越した。翌年クリーブランド音楽学校でピアノを習い始めた。ビートルズやモータウンの音楽は彼にとって初期の最も重要な影響力を持った音楽であった。
恵は10代の一時期、日本の高校でロックバンドをやっていたことがある。そして東京の国際基督大学に進んで、作曲と哲学を学んだ。
その後哲学科の卒業生としてカリフルニア大学サンタバーバラ校に編入した。1979年、文学修士号の取得まであと何単位かをとればよいという時にドロップアウトして、ブラジルの演奏家エアート&フローラ・ピュリムのバンドに正式に加わった。恵は彼らと1985年まで共演した。
これに続き、偉大なサクソフォニスト、ジョー・ファレルとも共演した。
「ジョーは僕の兄貴みたいな奴でね。僕が共演した初めてのモンホンのジャズ・ミュージシャンだった。フレーズやコードなどジャズ・ミュージシャンが知らなければいけない基本的なことを沢山教えてもらった。本当に彼はすごい奴だった。」
恵は17才の時からマイルス・デイビスを聞いていた。
「彼の影響はすごく大きいよ。でもマイルスとの共演に費やした2年間は、以前から持っていた音楽に対する信念をさらに強めたね。マイルスはいつも前進を心掛けていて、絶対に後ろは振り返らなかった。マイルスはその瞬間を生き演じるミュージシャンだった。そしてそれは僕にとってジャズの何たるべきかの源泉なんだ。」
恵は1991年にバンドを辞めた。「ああいった音楽(マイケル・ジャックソンの「ヒューマン・ネイチャー」のような)を演奏するのに疲れたんだ。ジャズ・ピアニストとしての原点にもどることにしたんだ。」
* * *
パリーと僕は、火曜日の夜に恵がトリオで演奏するのを見に、古河まで行くことにした。今回は、東京から彼の10代のあこがれのミュージシャンであったドラムの村上寛とベースの鈴木好雄を迎えての共演である。僕達は午後5時43分の古河行きの新幹線に飛び乗った。鈍行で行けば45分かかるところをたったの17分で着いてしまった。
場所はすぐに見つかった。古河は東北の他の街の御多分にもれず「田舎」の小さな街である。クラブ「花の館」はしゃれた雰囲気の落ち着いた場所で、気さくな経営者はニューヨーク・ヤンキースのTシャツを着てリラックスしていた。料金はまたしても7,000円で、サイド・ドリンク付きである。(この値段は、じきになれてくる。実際、客席スペースの狭さを考えたら理に適っており、日本でよい音楽を堪能するという特典には過当な割増し料金が伴うものなのだ。)
別の部屋には長いカウンターがあり、照明を柔らかにみせている。僕たちが本間さんやマリと一緒に座ったクラブ後方には、4つのテーブルと良質の革製の長椅子が拡がるように置かれていた。ミュージシャンのサインが黒いペンで壁に走り書きされていた。およそ20人位の人々がつめかけていた。ステージは狭く、バスとドラムとピアノを置いてちょうど位の広さだった。
ライブは本当の音楽を聴く唯一の方法である。また、小さなクラブが最適である。客は飲み放題の特権に便乗して騒がしかった。僕達のそばにはサラリーマンと思しき一団がいた。一人は合間ごとに「イエーイ!」とかけ声をを入れ続けた。
恵がリードをとる時は、はずみを付けて椅子から立ち上がり、躍動的に体を動かしながらも指は鍵盤の上を駆けめぐる。驚異的なテクニシャンである、がまた心の躍動を表現し得る水準まで突き進むアーティストでもある。
各々のソロが奇想天外な展開や技巧を駆使した感情豊かな旋律を奏でる。彼らがいつもは一緒に演奏していないとは信じ難い。素晴らしい演奏だった。
時計は既に11時を回っており、電車は走っていなかったので本間さんが新車のフォルクスワーゲンで僕たちを送ってくれると言った。
帰路、マリは僕たちと話しながら夫のために通訳していた。本間さんは近年、彼のオーケストラの初演に出席するためシンガポールに行って戻ってきたのだった。彼らは来週、二つの新しい仕事のために韓国に発つ予定であった。一つはマリが演奏する室内音楽の作品、もう一つはフルートとハープの作品。
恵は石巻の近くで演奏してからカリフォルニアに戻る前に1週間、東京に行く予定だった。彼は一月にカリフォルニア大学で音楽を教える仕事を始める。
「それが唯一の確たる収入源なのよ」
マリは姉らしい懸念をもらす。恵は少なくとも1年に1回は日本に戻るという。彼らの父、泰さんが函館に住んでいるからだ。
* * *
数日後、僕は先日の演奏がどうだったかを聞きたくてバリーに電話をした。
「僕は朝目が覚めたら足で拍子をとっていたよ、昼までずっとハミングしていた。」
バリーはとても嬉しそうにそう言った。僕達はこの二つのコンサートが、日本で見たうちの最高の演奏であったという点で意見が一致した。そしてこのような体験をもっと見つけ出そうと誓い合った。
© 1997 Norm Ibuki