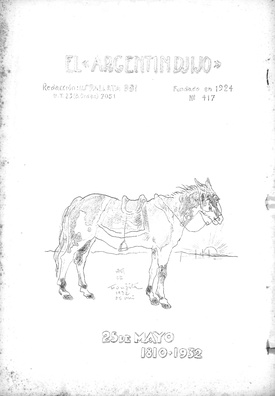レオナール・フジタ(別名:藤田嗣治)の名は今ではほとんどその輝きを失っているが、1920年代のパリで全盛期を迎えた世界で最も祝福された日本人画家である。フジタは、(ハリウッドスターの早川雪舟と並び)間違いなく最も有名な日本人であった。
1886年嗣治(つぐはる)として日本に生まれたフジタは、日本軍の将官を父に持ち、パリでアーティストになることを目指して1913年に日本を旅立った(パリでは姓の綴りを“Fujita”から“Foujita”に変更し、主に姓のみで通した)。
初個展でフジタは、中世のキリスト教と日本画図像を融合した金箔のような背景のある絵画など、さまざまな魅力的な画題を扱った。その後間もなくして描いた幽玄なパリの裸婦と物憂げな猫の肖像画は最も人気を博すことになり、数年のうちに“エコール・ド・パリ”と呼ばれる近代画家サークルの代表的画家となった。フジタの画法は、西洋の油絵に日本の木版画と墨絵の手法を取り入れたもので、細い線描で陰影を描くというものが特徴的だった。フジタは独自の乳白色を生み出し、それを“素晴らしき白”と呼んだ。その上に真っ黒の線描を重ねて描くと、ボヘミアンもブルジョアも共に彼の作品に魅了された。しかしフジタのマッシュルームカット(ビートルズより半世紀早かった)と特大サイズの眼鏡、小さい口髭、またその多くを自分でデザインしたという奇抜な衣装から成る派手な外見は、かなり不評だった。
ヨーロッパで16年間過ごした後、フジタは1929年から31年にかけて日本へ一時帰国をし、その後世界各国を巡った。3人目の妻を伴い日本に凱旋帰国した際、多くの好意的な論評が書かれた。例えば著名な小説家の川端康成は、モダニズム文学の名作『浅草紅団』(1929-30年)にフジタを登場させている。川端は、浅草のカジノ・フオウリイを訪れたフジタに注目し、作品の中で「パリイ帰りの藤田嗣治画伯が、パリジェンヌのユキ子夫人を連れて、そのレヴュウを見物に来るのだ」と記録した。
日本滞在後、フジタは渡米し、米国各地のギャラリーで作品展を開催した。1930年11月、ニューヨークに着いたフジタは、ラインハルトギャラリーズで展覧会を開いた。ここに10週間滞在し、滞在中は多くのアーティストと交流し、日本生まれのアメリカモダニズム画家・国吉康雄とも知り合った。1931年1月にはシカゴに移動し、アーツ・クラブ・オブ・シカゴで展覧会を開催した。
1931年3月にパリに戻ったフジタは、友人でありシュルレアリスム詩人のロベール・デスノスとユキが恋愛関係にあることを知り、彼女をデスノスのもとに残し(後に二人は結婚)、自身はラテンアメリカへの旅を決意した。皮肉なことに、フジタのラテンアメリカを巡るというアイデアは、デスノスの熱心なキューバ訪問の影響だったようだ。また、1920年代にかなり成功したので、フランス当局から高額な税金の支払い請求が来たことも、フランスを離れる一因となった。フジタは、カジノ座のダンサーでマディ・ドルマンという名で知られる新しい恋人、マドレーヌ・ルクーを伴い旅に出た。

フジタとマディの最初の訪問地はブラジルだった。2人はリオデジャネイロに4か月間滞在し、タイミングよく大晦日とカーニバルの時期を現地で過ごした。ブラジルの美術と文学の前衛者たちは、エコール・ド・パリの代表的画家であるフジタを温かく迎えた。パリで知り合った画家のカンディド・ポルチナーリがフジタを迎え入れ、エミリアーノ・ディ・カヴァルカンティやイスマエル・ネリなどの画家や、作家のマヌエル・バンデイラに紹介した。彼らは、機知に富んだ風刺や互いへの愛情表現にとどまらず、互いの画法を模倣しあった究極のオマージュを創作するなど、斬新な画法を交換しあい、交流を深めた。粋な恰好のフジタとマディが展覧会で来訪者を迎える様子を描いたネリの水彩画は、フジタとの短期間ではあるが、強烈な出会いを最も優雅に記録した作品だ。
ブラジルのモダニズム詩人であり音楽学者兼批評家のマリオ・ヂ・アンドラーヂは、1932年1月20日の『ディアリオ・ナショナル』の評でフジタの作品を称賛し、「知的芸術の世界は別として、非ヨーロッパ人種で根底の異なる芸術家が、ヨーロッパ芸術概念において重要人物となることに成功した珍しい例だ」と述べた。アンドラーヂは、フジタ作品の中心テーマを次の通り特定した。ヨーロッパ芸術の本質を忠実に再現する能力がないのではなく、意図的に“裏切っている”と。他の人々の解釈同様にアンドラーヂもまた、フジタは日本とヨーロッパ芸術を融合させることには無頓着だったと論じている。むしろフジタの作品の特徴は、「塑性的ともいえる徹底した静寂さであり、彼の絵画やスケッチには深遠な空虚さが描かれている。鋭い線描、広い余白、テーマを見事に表現するその手法、相対的清涼感があり、穏やかな表現方法、彼の作品に見るこうしたすべての要素が最終的に私を驚嘆させるのだ」。
フジタは、絵画制作に十分な時間を費やした。代表的な肖像画の制作は続けたが、南米中を旅したことで、自身の典型的スタイルから脱却し、新しいスタイルへと移行した。フジタが論争を招くのは初めてではないが(最後でもなかったが)、より幅広い絵具の色で多様な人種や社会階級を描くことに専念するようになった。予想通りフジタは、『Carnival in Rio de Janeiro(リオデジャネイロのカニ―バル)』や『À la porte au Carnival(カーニバルの後)』では四句節前の祝祭の光景を描いた。赤線地区の風景に魅了されたフジタは、売春宿の窓の内側から見た乱れた服装の4人の女性たちを描き、地区の名前から単に『 Mangue(マンゲ)』というタイトルを付けた。
さらにフジタは、リオデジャネイロ都市部の活気ある街角の暮らしを描いた。それはフランスびいきの上流社会が好む彼の作品の特徴でもあるモダニズム画題からの脱却の現れだった。『Deux gamins nègres(二人の黒人の若者)』には、苛立ちながら退屈する若者が描かれ、彼らは画面の外をじっとにらんでいる。『リオの人々』には5人の黒人女性の姿がバランスと取れた構成で描かれている。物憂げな表情を浮かべ落ち着かない様子で両手をいじる若い母親の隣の前景には2人の裸足の少女が立っている。他の2人の女性は両手を腰に当てて肘を張り、真っすぐに立っている。このうちの1人は背中を向け、もう1人はいかめしい表情で左を向いている。構図の中心の小さな少女だけが画家を直視しており、彼女たちのスケッチを描くフジタを前に、訝しげに頭を少し傾けている。
このようにして、中間色のベージュをしばしば背景に用いた民族誌的なスケッチを実験的に始めるようるなった。非の打ちどころのない線描と陰影はこの頃も健在だったが、入り組んだ生地や織物への関心は、パリの寝室のブロケードカーテンやベッドリネンではなく、民族衣装を描くことに直結した。フジタはこの新しいアプローチを南アメリカを旅しながら熱心に追求し、1933年の日本への帰国後も長く続けた。帰国後の作品では“エキゾチック”な画題も扱い、『ちんどんや職人と女中』(1934年)ではカーニバル風の都市の路上演奏家を描き、1938年には入れ墨のある沖縄女性と彼女の2人の孫娘を華やかな南国風の背景と共に描いた。
意外かもしれないが、ブラジル滞在中のフジタは日系ブラジル人メディアからはほとんど見過ごされていたようだった。当時、日系ブラジル人コミュニティの圧倒的多数がサンパウロ州内陸のコーヒー豆農園や農業入植地に集中していた。このコミュニティはまだ若く、総勢10万人規模だったが、1930年代前半に急速に成長した。そしてその6割以上は、過去5年以内に日本から到着した人々だった。
フジタが滞在期間のほとんどをリオデジャネイロで過ごし、サンパウロには遅れて1月に到着したこともメディアの注目に欠いた理由だった。フジタは、魅惑的で晴れの日の多いリオデジャネイロほど、灰色の商業都市のサンパウロには魅了されなかった。ポルチナーリへの手紙には、「ここは寒くて雨が降る」と不満を綴り、「我々はリオでの滞在をとても楽しんだ」と付け加えた。実のところ当時は大恐慌の最中で、1931年9月18日に満州事変が起こり、日系メディアの見出しを占めていたのは日本とブラジル国内の幅広い政治状況だった。日系日刊紙の5つののうち、フジタの訪問を報じたのは、唯一1932年1月1日『日伯新聞』付録のポルトガル語コーナーだった。フジタは、「世界中のすべての文化都市で尊敬されているモンマントルとブロードウェイのアイドルの一人」と称えられた。
フジタのブラジル訪問にメディアが注目することはなかったものの、フジタは日系人のコミュニティーと交流をもった。1935年に日系人モダニズム画家による「聖美会」を共同で立ち上げた若い日系一世の画家、半田知雄と高岡由也とも出会っている。フジタは他に田中重人ウォルター、富岡清治、玉木勇治、桧垣肇、高橋吉左衛門や、作家の古野菊生、木村義臣と会った。フジタの影響はこの一時にとどまらず、1935年に作家のオリジェネス・レッサが、不幸な終わりを迎えた“ブラジル版フジタ、国民的フジタ”となった若き一世画家の短編を執筆した。戦後フジタは、サンパウロ訪問時に知り合ったジョージ・モリなどの数人の才能ある二世をパリに迎えている。
ブラジルを離れ、その後はアルゼンチンで5ヶ月過ごしたフジタは、驚くほど華々しく迎えられた。複数の資料によると、フジタの展覧会には6万人が押し寄せ、1万人のファンがサインを求めて列を作った。言うまでもなく展示作品は完売し、カロリタ・カルカノ・デ・マルティネス・デ・オズなどからは、直接肖像画の制作依頼が入った。
ブラジルより極めて小規模のブエノスアイレスの日本語メディアとの関わりは、ブラジルの時よりもよかった。フジタは、ブエノスアイレスに拠点を置く『亜爾然丁(アルゼンチン)時報』(スペイン語では『El Argentin Djijo』)の1932年5月号に、サイン入りでガウチョ(訳注:アルゼンチンなど南米の草原地帯のカウボーイ)の定番イメージである馬のイラストを描き、アルゼンチンの独立記念日への短い祝辞を寄せた。ブラジルや米国の確立された日本語新聞とは異なり、当時の『アルゼンチン時報』はまだガリ版刷りだった。
アルゼンチンで何都市かを訪れた後、フジタはボリビアとペルーへと旅を続けた。美術史家の山梨絵美子は、『Japan & Paris』に、フジタの随筆集『地を泳ぐ』(1942年)の「南米展望」という章から次の通り引用している。
私の永年の海外生活中、又私の一生涯を通じて再び得難い体験中、湖水についての自慢話と聞かれるならば、何を措いても第一に南米ボリビア国とペルー国とに挟まれたチチカカ湖をあげるのである。
フジタが個人的な意見を明らかにするのは珍しかったが、公の声明の中でもこの記述は極めて典型的だ。日本や南米の批評家が、落胆したと酷評した『ラマと四人の人物』(1933年)などの作品には、鑑賞者が期待する華やかな現代的生活とは著しく対照的な風景を描きたいというフジタの願望が表れていた。
1932年10月28日、フジタとマディはキューバに到着した。メキシコへと旅を進める前に立ち寄ったカリブ海の唯一の国だった。キューバ滞在についてはほとんど記録されていないが、それはハバナの素晴らしい魅力を画家自身の中に留めておきたかったからか、それとも酌量すべき事情があったからなのか、さまざまな解釈の余地がある。伝記作家のフィリス・バーンバウムによると、フジタとマディのいつものボヘミアンな悪ふざけが原因で二人はトラブルに巻き込まれることがあり、「あるキューバ人記者は、『マディは酔っぱらった交通警官よりひどい騒動を引き起こした』と記していた」。(『Glory in a Line』P.168-169)
© 2021 Greg Robinson & Seth Jacobowitz