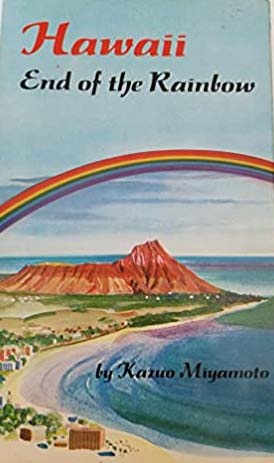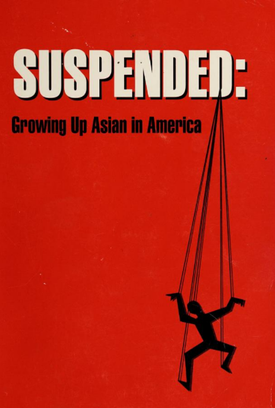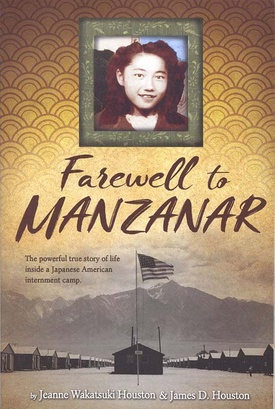戦後、1960年代後半から1970年代にかけて、日系アメリカ文学は全体的に比較的不足しており、公民権運動やブラックパワー運動は日系アメリカ人のメディアで大きな注目を集めたものの、この時期に出版された日系アメリカ文学に目立った影響はほとんど及ぼさなかった。
例外的なのは、ジョー・アイデ(別名「ジョセフ・パトリック・アイデ」や「ジョセフ・アイデ」)が羅府新報のホリデー版に定期的に寄稿している点です。アイデはロサンゼルス南部に住み、1951年からオール・ピープルズ・クリスチャン教会/センターで働き、1984年に退職し、1977年に事務局長になりました。その期間を通じて、彼は羅府新報のホリデー版に毎年記事を寄稿しており、そのほとんどは自伝的記事や彼の家族に関する記事でした。彼はアフリカ系アメリカ人を含む多民族地域で暮らし、働いていたため、彼の記事にはアフリカ系アメリカ人の登場人物が時々登場します。
特に興味深い例は、1969 年の寄稿「私が 21 歳のとき… それはとても良い年だっただろうか?」である。息子の 1 人が 21 歳になったことに触発されて、イデは 21 歳のとき自分と仲間が直面していた非常に異なる世界について回想している。また、息子のクラスメイトの 1 人であるマックという名の若いアフリカ系アメリカ人の男性の話もしている。マックは「静かで、目立たず、話しかけられなければ決して話さない」人物だったが、大学で 2 年間過ごし、アフリカ系アメリカ人の学生組織に関わった後、「黒人学生の間では闘争的な活動家、怒れる活動家」に変貌した。イデはまた、マックを息子の引き立て役として使い、マックの人種に基づくジレンマ (これは二世がかつて直面していたものと似ているとイデは示唆している) と、息子が直面した教育、職業、デート/結婚といったより普遍的な問題とを対比させ、三世はアフリカ系アメリカ人や二世と同じような人種問題に直面していなかったことを示唆している。何年も後、アイデの息子の一人(同じく「ジョー・アイデ」という名で知られる)は、アフリカ系アメリカ人を主人公にしたベストセラーの犯罪小説シリーズの著者となった。
対照的に、アフリカ系アメリカ人を登場人物とする1960年代の日系小説、宮本一夫の『ハワイ 虹の果て』は、あたかもそのような社会運動がまったく起こらなかったかのように読める。しかし、これにはいくらか説明がある。ハワイ出身の医師で年配の二世(1897年生まれ)である宮本は、第二次世界大戦中にアメリカのさまざまな強制収容所に収監されている間に自伝的小説を書き始め、アフリカ系アメリカ人に関する部分は1920年代を舞台にしている。
この小説では、ミヤモトの分身であり主人公である村山実が、1924年から1927年までミズーリ州セントルイスのワシントン大学の医学部に通う。彼は75人の学生のうちの1人で、唯一の非白人である。ミノルは当初、「[新しい]友人たちの心の広さと温かさ」を楽しみ、「みんなの間にある善意」に注目する。彼はまた、市内のアフリカ系アメリカ人コミュニティに興味をそそられ、ブッカー・T・ワシントンの「大ファン」であると公言している。そのため、温厚な研究室のパートナーであるマリネックスがアフリカ系アメリカ人に対してあからさまな敵意を示し、コロンバスでのリンチを見たことを話し、「唯一の良い黒人は死んだ人だ!」と言ったとき、彼はびっくりする。ミノルは、こうした態度を非難する姿勢を明確にしつつも、それが理解できることも説明している。より制限の多い南部の地域からセントルイスに移住してきたばかりのアフリカ系アメリカ人は「この自由を行使する際に傲慢になる」ため、白人を苛立たせるのだと指摘している。(ミノルは、10年も経たないうちに隣のイーストセントルイスで起きた大規模な黒人差別の虐殺については何も触れていない。)これは、1964年に出版された小説の中では奇妙なほど時代錯誤な一節である。特に、ミノルが執筆の目的の1つは「アメリカが過去のひどい過ちを繰り返さないようにすること」だったと書いていることを考えると、なおさらである。
セントルイス滞在中、ミノルはアフリカ系アメリカ人の患者や医療スタッフと直接会う機会も数多くある。地元の病院の黒人病棟で勤務中に、最初は敵意を抱いた「大柄な混血」の患者に出会うが、3 週間の入院中にミノルは患者を味方につける。後に、プルマンのウェイターであるブラウンという「非常に知的で、清潔感のある若い患者」との出会いについて述べている。ブラウンが医学部へ進学したものの差別に直面して医師を辞めたと知ると、ミノルはブラウンが自分の人々に対する義務を「怠った」と叱責する。後に、産科研修について述べる際に、ミノルは「学生は皆、貧しい白人の家庭よりも黒人の家庭を好んだ」と述べている。黒人の家庭は「より感謝の気持ちがあり協力的」で、家庭の方が清潔だからである。卒業後、ミノルはインターンシップを確保しようと試みるが、人種差別に遭遇するのは初めてだという。ここで、彼は、勤務できる病院の数が限られているアフリカ系アメリカ人(およびユダヤ人)の医師たちとの共通点を見出す。その途中で、彼はセントルイスの「黒人」病院を訪れ、その病院のスタッフが「どの職場でも優秀だった」ことを知った。セントルイスでの 4 年間で、ミノルはアフリカ系アメリカ人の苦境をより深く理解するようになり、最終的には、日系アメリカ人として人種差別に直面した際に、ある程度、彼らと共感するようになった。
後年の作品で、セントルイスを舞台にした「ハワイ:虹の終り」の部分と共通する特徴を持つのが、2000年に出版されたクリフォード・I・ウエダの回想録「Suspended」である。ウエダは、西海岸での教育差別に直面し、ニューオーリンズのチューレーン大学で医学を学びながら第二次世界大戦中を過ごした様子を述べている。「白人」として受け入れられたものの、当時の人種差別が不当で不合理であると感じ、ウエダは不安を感じていた。ウエダは、職場で黒人の学生と交わした会話を述べている。その学生は、アメリカの歴史を教えたいと考えており、ジム・クロウ法の規制を受けない北部の大学に入学したいと説明し、ウエダはそれが西海岸からの自身の移住と似ていると見ている。
一方、 『ハワイ 虹の果て』の8年後に出版されたハワイの二世による別の小説は、宮本作品と異なる形で類似している。ジョン・シロタの1972年の小説『パイナップル・ホワイト』も、ハワイ出身の日系アメリカ人が大陸に渡り、自分にとって馴染みのない人種的態度に遭遇する物語である。しかし、今回は、著者はこれらの遭遇を主にコメディとして扱っている。
パイナップルホワイトは、主人公の斉木次郎(65歳の元農園労働者)が、1949年に息子と嫁と共に老後の余生を過ごすためにハワイからロサンゼルスへ旅する様子を描いています。物語は次郎が大都会生活に戸惑う様子を中心に展開されますが、彼の戸惑いの多くは、彼がハワイで慣れ親しんだ人種構成とロサンゼルスの人種構成の違いに起因しています。息子の光雄とドライブ中に初めて到着した次郎は、「カナカがすごく多い」と述べます。これはハワイ先住民の俗語です。息子はこれを面白がり、「彼らはカナカではなく、黒人だ」と老人に言います。次郎は、「彼らはワイパフのモクの子供たちによく似ている」と答えます。人種に関する彼の混乱は小説全体を通して続き、彼は出会うラテン系のタクシー運転手、そして基本的に肌の色が濃い人は誰でも「カナカ」に違いないと主張します。息子の白人の義母にハワイにはアフリカ系アメリカ人がたくさんいるかと聞かれると、次郎は「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」と答える。「ワイキキビーチには黒人の少年がたくさんいる」。ハワイ先住民はアフリカ系アメリカ人と同じではないと義母が答えると、次郎は「何が違うんだ?… 黒人より黒人のカナカ人もいるし、カナカより黒人の日本人もいる」と答える。
いつも人当たりの良いジローは、本の中で多くのアフリカ系アメリカ人の登場人物と交流し、リトル トーキョーで新聞を売っているアフリカ系アメリカ人のサミーと友情を築きます。ジローが出会うすべての人を素朴だが心を開いて受け入れる様子を暗に受け入れながら、パイナップル ホワイトは、アフリカ系アメリカ人も他の人たちと同じように受け入れられるべきだというメッセージを伝えています。
翌年、ジーン・ワカツキ・ヒューストンとジェームズ・ヒューストンの『マンザナーへの別れ』が出版された。これは日系アメリカ人による日系アメリカ人強制収容に関する本の中でおそらく最も広く読まれている。マンザナーで一部収容されていた幼少時代を振り返る大人の視点で書かれたこの本には、マンザナーの「肌の色が薄い混血の」隣人について語る一節がある。幼いジーンは収容所でその女性の養女と遊び、その女性が「収容所の誰よりも背が高く」、「頭にアント・ジェミマのスカーフを巻いていた」と述べている。大人になったジーンは、その女性が実はアフリカ系アメリカ人であり、髪を覆っていたのは日系人の夫と子供と一緒にいられるように日本人に成りすますためだったと悟る。
続く…>>
© 2022 Greg Robinson, Brian Niiya