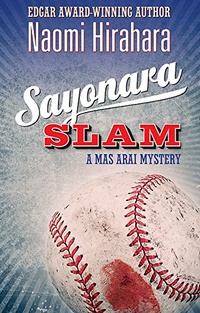オレンジ郡の刑事2人はボディーガードのケンジを連れてサチのホテルの部屋を出た。「もっと聞きたいことがある」とフラナガン刑事はケンジに言った。「バック氏が亡くなった晩、あなたが彼から離れていた間に何をしていたのか、1分ごとに詳しく聞きたい」
まあ、少なくともそのうちの27分くらいはホテルのバーで私と一緒にいたんだ、とサチは思った。折り紙のプロジェクトでミスをすることが最大の悩みだったあの頃に戻れたらいいのに。ケンジはうなずいて別れを告げた。「これが終わったら電話するよ。」
ドアが閉まり、サチは最近掃除された部屋に一人残された。ルームメイトのベッドのカバーの角を除いて、すべての物が完璧な状態だった。過去 2 日間の混乱はすべて消え去っていた。
どうしてこんなことになったのか、サチは不思議に思った。どうして殺人事件の捜査に巻き込まれたのだろう?救急室では、常に犯罪の余波に対処していたが、今やサチと彼女の新しい友人たちは、犯罪を犯した容疑者として見られている。
サチは携帯電話を取り出し、親友のレスリーに電話した。応答はなかった。レスリーは週末も働いており、おそらくまだ勤務中だったのだろう。彼女は共通の友人で、病に伏せていた看護助手のオスカーのことを心配した。サチは特に信仰深い人間ではなかったが、善い考えは信じていた。たとえそれが亡き夫の役に立たなかったとしても。彼女はオスカーに一通のメールを送り、それからレスリーにテキストを送った。
彼女はテレビのリモコンを手に取ったが、無数のチャンネルがあるにもかかわらず、見たい番組は何もなかった。折り紙をしようかと思ったが、クレイグ・バックのことが頭から離れなかった。折り紙に毒が仕込まれていたのだろうか?それが彼を殺したのだろうか?もしそうなら、彼女も簡単に殺されていたかもしれない。
彼女はカーペットの敷かれた床の上を歩き回った。もう一人でいるのが耐えられなかった。オリビアは今や管理上の危機から解放されたのかもしれない。サチはオリビアの携帯電話番号を持っていないことを思い出した。彼女はペントハウスのホテルのオペレーターに電話をかけ、結局留守番電話にメッセージを残すように指示された。
サチは急いで化粧を直した後、ハンドバッグを持ってホテルの部屋を出た。彼女は、きちんと家具が備え付けられた独房に閉じ込められたままでいるか、あるいは何が起こっているのかを正確に把握しようと試みるかのどちらかを選んだ。
* * * * *
サチはエレベーターでペントハウスに向かった。ドアが開くと、すぐに廊下の大きな革張りの椅子に座っているオリビアの息子で、折り紙の達人でもある12歳のタクが目に入った。タクは必死に折り紙を折っていて、床には折り紙の動物が散らばっていた。明るい緑のライオン、赤いカエル、黄色いフラミンゴ。サチには、タクがわざと色を合わせていないのか、それとも困惑のサインなのかわからなかった。
「タク、ここで何をしているの?」彼女は正直タクが好きではなかったが、彼はまだ子供だということを自分に言い聞かせた。すべての子供には二度目のチャンスが与えられるべきだ。
「両親が口論しているんだ」と彼は閉まったペントハウスのドアを指さしながら言った。
「彼らはあなたがここにいることを知っていますか?」
彼は肩をすくめながら折り続けた。「彼らはたいてい私がどこにいるか気づかないんです。」
サチは悲しみに震えた。彼女は自分が「子供好き」だとは思っていなかったが、姪や甥の間では人気者だった。おそらく、彼女には彼らに何も期待していなかったからだろう。他の看護師たちは、彼女は子供、特に幼い患者と仲が良いとコメントした。それは、彼女が彼らを手足やバカとしてではなく、同じ人間として扱っていたからに他ならない。
彼女はカーペットの上に足を組んで座り、拓の紙作品が潰れないように気を付けていた。拓は素晴らしい折り方をする人で、いつも鮮明で力強い線を描いていた。
タクはサチに一枚の紙を差し出した。黒い四角。サチはたいていその色でペンギン、シマウマ、コウモリ、パンダなどを描く。しかしタクは予想外のものを描いていた。
彼女は一息ついて考え、それから作業を始めた。二つのこぶは簡単だった。難しいのは耳の部分だった。タクの技術がサチにも伝わったようで、作業が終わったとき、サチは実際に誇らしい気持ちになった。
「黒いラクダだ!」タクの声は甲高く、12歳とは思えないほど幼く聞こえた。「スターウォーズに出てきそうな感じだ。」
サチはそれを褒め言葉として受け取り、伸ばした手のひらにそれを少年に差し出した。
「君は見た目以上に優秀だよ」と彼は言った。
それは意味不明でありながら、同時にとても意味をなす奇妙なコメントだった。彼女の夫スコットはよくそのようなことを言っていた。彼女は自分自身を過小評価し、その結果、期待したパフォーマンスができなかった。おそらく、クレイグ・バックのマスターセッションで起こったのもそれだったのだろう。彼女はプレッシャーに負けてしまったのだ。
「ケンジは君についてそう言ってるよ。」
「ケンジ?」タクの口から彼の名前が出てくるのは奇妙に聞こえた。サチは彼がミスター・バックのボディーガードを知っていることにさえ気づいていなかった。
「ああ、彼は私の母にそう言っていたんだ。」
サチは頭に冷たい水をかけられたような気がした。「どういう意味?」
「彼は実際、君は見た目より賢い、と言っているんだ。母は気をつけた方がいいって。」タクは折り紙から顔を上げた。「彼が何を言っているのか分からなかった。」
「タクさんにとってケンジって何なの?」
"彼は私の親友だ。"
「彼は君の友達になるには少し年を取りすぎているんじゃないの?」
「実は、彼は私の母の親友だったんです。母が彼に家を出るように言うまではね。」
サチは固くなった。「つまり、彼はあなたと同居していたということですか。」
タクはうなずいた。「その後、彼はバック氏のもとで仕事を得て、メキシコに移住したんです。」
「ニューメキシコ」サチはつぶやいた。かつては、自分が折り紙のエリートたちの側近の一員であると感じていたが、今は、自分がこの人たちがどんな人たちなのかまったくわかっていないことに気づいた。自分がなんて愚か者なんだと感じた。一瞬、ケンジは恋愛対象になるかもしれないと思った。しかし、彼は、すべての男性が夢の中で追い求めるような神秘的な美女の一人に執着していた。
サチは警察が何を言ったかなど気にしなかった。今すぐにでもあのホテルから脱出しなければならなかった。
彼女は立ち上がった。
「もう行っちゃうの?」タクは悲しそうな声を出した。
するとエレベーターがカチッという音をたてて開き、緑のカシミアセーターを着た健二が現れた。
「サチ、君がここに来てくれて嬉しいよ」と彼は言った。
彼女は、彼が警察に乱暴に扱われることを願った。しかし、彼は完璧に見えた。残念なことに。
もしサチが別の人間で、30歳くらい若かったら、彼女はその完璧な顔を平手打ちするか、板のように割れた腹筋にパンチをくらわせていただろう。あるいは少なくとも、その場で蹴りを放っていただろう。
彼女は背筋を伸ばしてまっすぐ彼のところへ歩いて行きました。「あなたが正しいのよ」と彼女は言いました。「私は見た目より賢いのよ。」
そして彼女は開いたエレベーターに乗り込み、降りるボタンを押しました。
コンテストのお知らせ
誰が折り紙作家を殺したかわかりますか? コンテストに参加してください!
優勝者には、平原尚美の近刊ミステリー小説『さよならスラム』のサイン本が贈られます。ドジャースタジアムで行われたワールドベースボールクラシックを舞台にした『さよならスラム』は、平原のマス・アライ・ミステリーシリーズの第6作です。
下のコメント欄にあなたの推測を書き込んでください。殺人犯の名前を明記し、 2016 年 5 月 3 日火曜日の午前 0 時 (PDT) までに推測を送信してください。同じ推測をするコメントが複数あっても問題ありません。正しい推測の中から、著者がランダムに勝者を選びます。
このコンテストに参加するには、ここで推測を投稿する必要があります。勝者は第 11 章を投稿した時点で発表されます。勝者には、このサイトで登録/コメントする際に使用したメール アドレスを通じて連絡が届きます。10 日以内に返信がない場合は、別の勝者が選ばれます。
このコンテストに参加できるのは、アメリカ合衆国 50 州およびコロンビア特別区の居住者のみであることにご注意ください。
『Death of an Origamist』を読んでいないですか?第 1 章から始めてください。
読んでくれてありがとう!
© 2016 Naomi Hirahara